ニセコ町内進出企業紹介・ニセコ蒸溜所

ニセコ町での事業展開により、まちの魅力向上と課題解決に貢献。銘酒「八海山」を手がける八海醸造とニセコ蒸溜所社長 南雲二郎さんにお話しを伺いました。
会社と商品・サービス
南雲さん:新潟県南魚沼市の八海醸造は創業1922年、南魚沼地域一帯の町おこしのひとつとして祖父が設立しました。酒蔵以外にも病院や製糸工場などを建設し、地域経済の発展に貢献。祖父が亡くなった後は、父親が八海醸造を受け継ぎました。また、叔父は獣医から医者へ転身し院長として、地域の医療を支えてきました。会社発展を通して地域に貢献してきた一族なので、私もそれらの意思を尊重して八海醸造を継ぎました。
八海醸造・ニセコ蒸溜所は、発展と継続を志しています。企業によって発展・継続の意味は異なりますが、食品・嗜好品業では「地域からの協調・共感」が不可欠です。全国での売上が上がっても地域との繋がりがなければ継続しない。実際に食品メーカーは需要がある土地で創業した方が多く、愛着を持ってくれる住民がいることが重要で、単純に高品質な商品をつくるだけでは意味をなさないのです。

ニセコ蒸溜所は2019年に創業し、製造しているクラフトジン「ohoro GIN(スタンダード)」が「World Gin Awards 2024」で世界最高賞である「World’s Best」を受賞、「International Spirits Challenge 2024」でトロフィー(ジン・カテゴリー最高賞)を受賞しました。世界の名立たるコンテストで評価をもらい、製品への思想は間違っていなかったと実感しています。
そしてohoro GINがニセコ町のご家庭にある光景が何よりの幸いです。日本の大衆が魅力を感じ、毎日飲めるジンを目指したのです。お酒はコミュニケーションツールだと思っていて、より豊かな時間を過ごすためのもの。過度に香りと味に独特さを出さず、バランスの良い調合で飲みやすいお酒を造りました。
その他、新潟では麹甘酒や焼酎等も製造し、アンテナショップや複合施設運営などを幅広く展開しています。
ニセコ町に進出した経緯
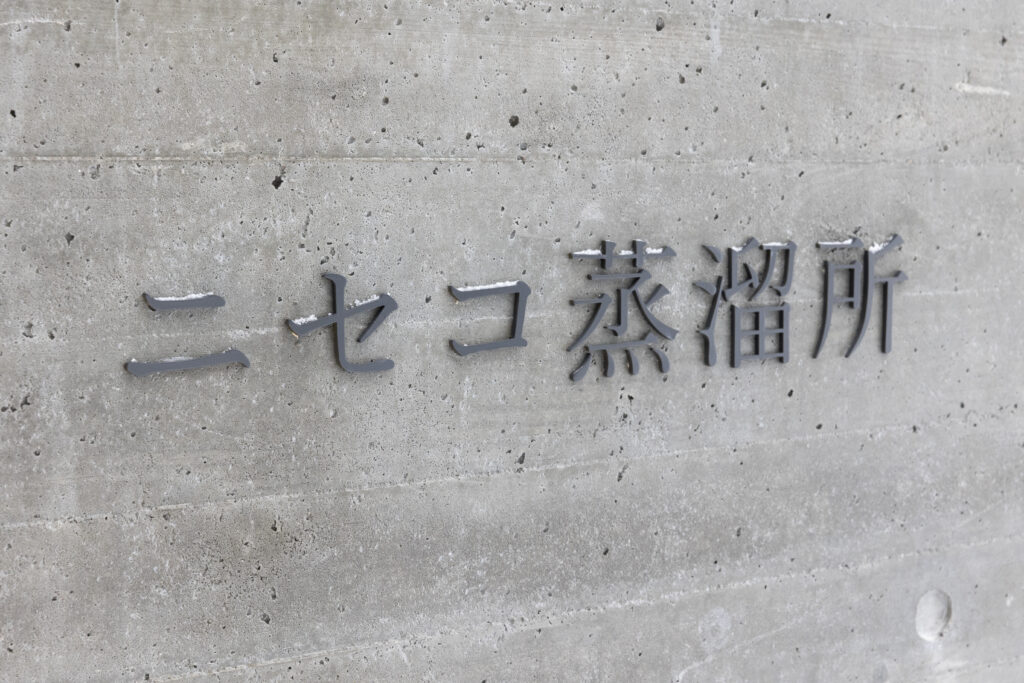
15年前、スキーでニセコに初めて来たのをきっかけに、営業担当だったので酒の会を開くようになりました。そこで片山町長と出会いました。ニセコの方々と交流する中で、新潟もスキーリゾートなので地域課題(冬のリゾート開発とオフシーズン対策)が似ていて、親近感が湧き、グリーンシーズンも滞在しました。特にニセコ町は乱開発をしない政策があることに共感しました。
新潟の魚沼は何もなかったところですが、現在、八海醸造の酒蔵を中心に展開している複合施設「魚沼の里」にはレジカウントだけでも年間30万人以上が訪れています。とても有難いことですが、観光客が多すぎると、その地域の自然環境・方針が乱れてしまうことがあります。また、むやみやたらに建物をたてる開発もしたくありません。目立たない土地で自然に溶け込み、屋内は空間を広く感じられるが外からは大きく見えない、かつ経年劣化しにくい設計を心がけています。このような想いから、ニセコ町の政策に惹かれたのです。

ニセコ蒸溜所正面
2016年から新潟では、ウイスキー製造を開始。きっかけは製造した米焼酎に色がつきすぎると法律上、焼酎としては販売できないので、米ウイスキーにしてみようという試みでした。そして、美味しいお酒を造るには、長期低温熟成が重要だと痛感していたので、気温が低く丁度良いニセコが良いのでは?と考えるようになりました。
その後、ニセコ町役場に相談に行ってみると、町長・副町長が歓迎してくれ、受け入れてくれました。新たな地で事業展開を踏み出すには、気候・自然環境・話題性・将来性など、総合的に判断するので土地を深く理解していないといけない。ニセコ町役場との関りがあったから、実現できたことです。
事業展開後の反響
町民の皆さんから「ジン、美味しいです。早くも賞をもらって凄いですね!」「ウイスキーはいつできるの?日本酒は?」などの喜ばしい声をいただきます。

一般的にジンはカクテルベースで飲むもので、習慣として飲んでいる日本人は少ないと思います。そこで、ohoro GINは、過度に個性を出さず、ジンだけでも飲みやすいものにしました。日常消費材として、いつでも誰でもどこでも飲めるものを目指しているので、コンビニでも販売しています。
世界の名だたる賞の受賞を町民も喜んでくれたことがとても有難いです。商品が世の中に広がり、賞をもらったり、他地域の店頭でみつけたら、町民が自慢に感じるような愛されるものを今後も造っていきます。
ウイスキー製造には長い年月を要するため、ニセコ蒸溜所での販売は2032年以降の予定です。先に製造を始めた新潟・八海醸造では、今年ウイスキー販売を開始する予定です。せっかく2拠点で造っているので、将来的にはブレンドしたり、ブレンデッドウイスキー(シングルモルトウイスキーとグレーンウイスキーのMIX)も考えています。
ご好評の日本酒「ニセコ蝦夷富士」は、ニセコで育った酒米を使い、醸造は長年培った技術技術を活かすため新潟で行っています。ニセコと新潟・魚沼の水の成分が似ているので、今後はニセコでも造れるのではとも思っています。
また、事業展開には地域貢献が不可欠なので、お酒以外でも蒸溜所に来る楽しみとして、地域の方々を招いたイベント等を開催しています。パウダースノーの景色が魅力的という理由で、結婚式の披露宴を行う方もいて、このような発想はなかったとスタッフも驚いています。
多様な利用方法を通して、ニセコ蒸溜所を知ってもらえ、嬉しい限りです。

地域に根差した事業展開
ohoro GINの原料には、ニセコ町産のヤチヤナギ、ラベンダー、ニホンハッカを使用するなど、地域資源を活かすことにも取り組んでいます。
ラベンダー栽培は、ニセコ高校と協力したプロジェクトを行い、商品は大ヒットを記録。すぐに売り切れるほどです。また、ニセコ高校の卒業生でニセコ蒸溜所に入社してくれた方もいます。雇用創出にも繋がり、とても心強く感じています。
弊社製造メンバーとニセコ町の契約農家さんは、原料の調達や製造における協力体制を築いています。特に酒米栽培においては、密接な連携が重要なので、弊社の方針も理解してくれています。
今後のビジョン
これからの時代は、観光としての飲食産業の割合が増えていき、味の差だけで商品を選ぶ消費者は減っていくと思っています。そこで、商品のクラフト化が重要です。地域性のある商品開発と地域の魅力を感じる仕組みを作ること。例えば、旅先の農家で野菜を試食した後、移動したレストランで同じ野菜を別の調理法で食べて美味しかったなど。地域の魅力をストーリー性も含めて発信することが鍵です。
ニセコ蒸溜所ではラベンダージンに続く、特産品の開発が期待されており、地域の方とトウモロコシ畑を作り、そのトウモロコシを使った新商品やまた、じゃが芋を使ったウォッカも良いなと思っています。
蒸溜所は観光施設としても役立てたく、ニセコ発・世界をテーマに、外国人へ日本の伝統工芸も伝えたい。それを北海道と北陸の観光資源活用に繋げていきたいです。観光客が地域を知ることも旅の楽しみの一つですしね。今後の展開も楽しみにしていてください。
ニセコ蒸溜所WEBサイト:https://niseko-distillery.com/ja/



